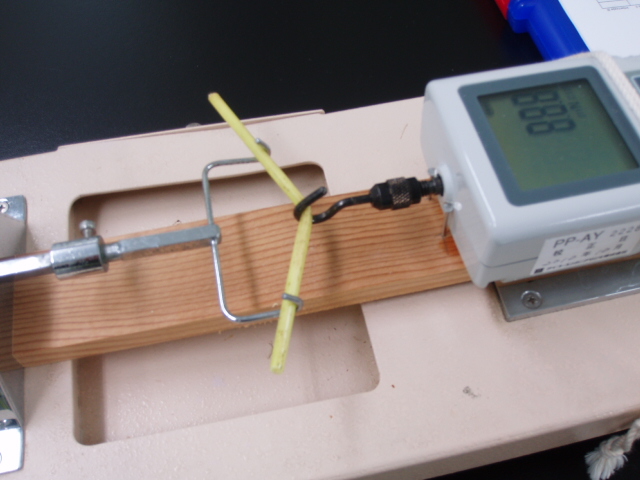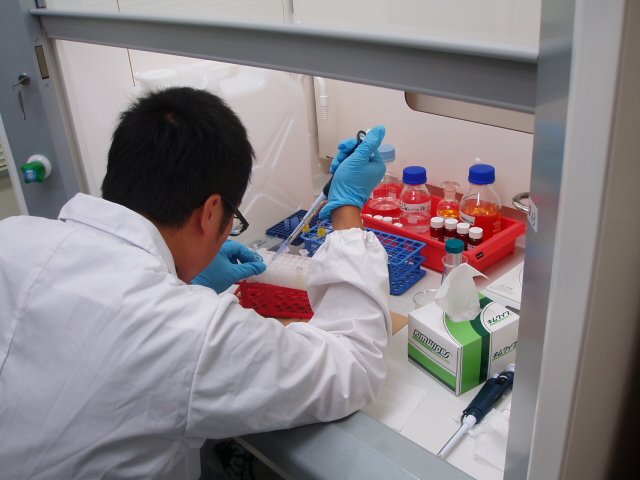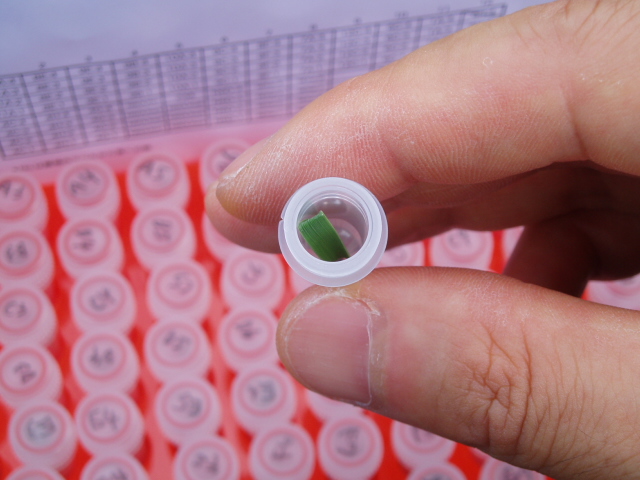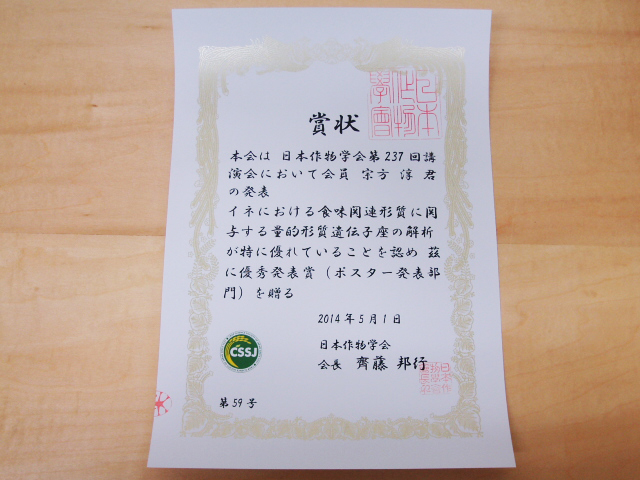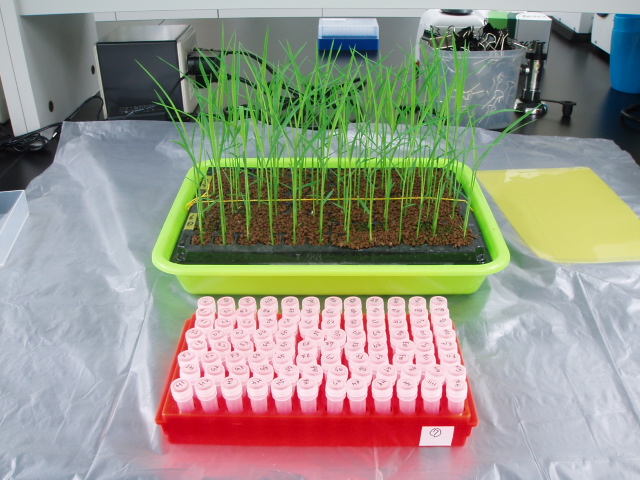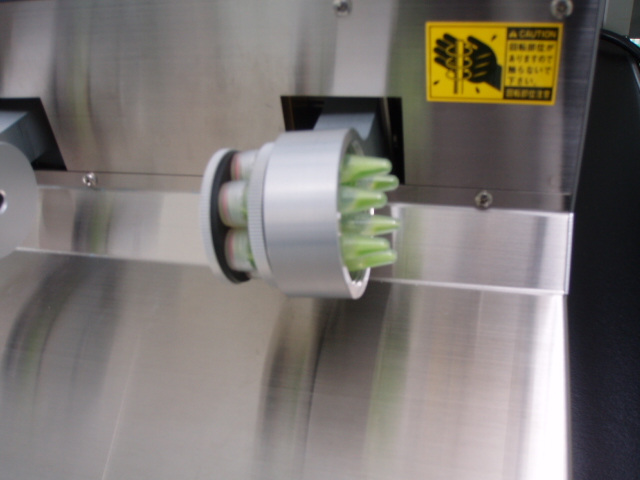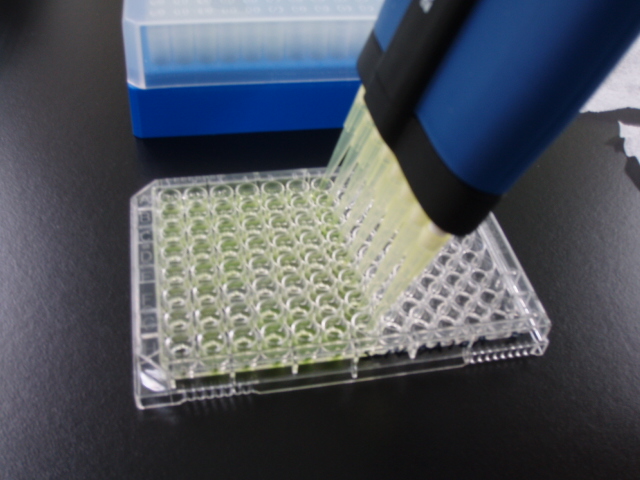11月に入り、徐々に寒くなってきました。
研究のためのサンプリングも無事終了し、水田圃場から離れる時期です。
少し寂しい気がします。
昨年と同様に今年も水田圃場に感謝をしつつ、秋起こしをしました。
有機物の分解や雑草の防除など、秋起こしによる効果は知られています。
春起こしから始まり、秋起こしで終わる、当たり前ですが重要ですね。
ついでに畦の補修もして、今年度の水田圃場作業は終わりです。
冬が来る前にしなければならない作業がもう1つ。
来年度春に学生実験で使うコムギとオオムギの播種です。
畑を耕し、畦を作って播種。
あとは稲藁でマルチングでもしておきましょう。
さて、次は採取したサンプルの測定と種子の整理。
やることはまだまだありますが、こつこつやっていきましょう。