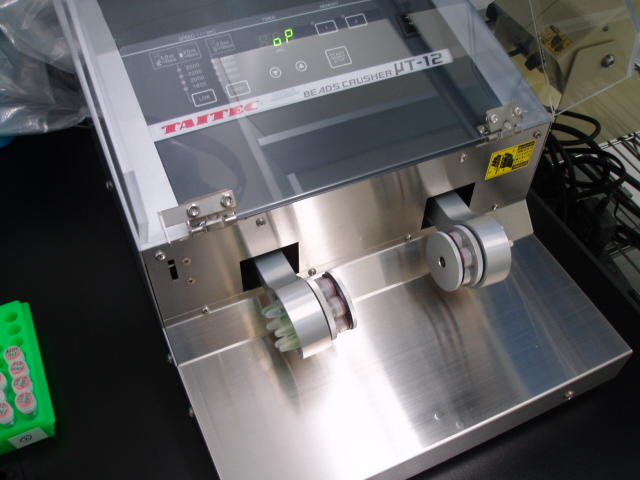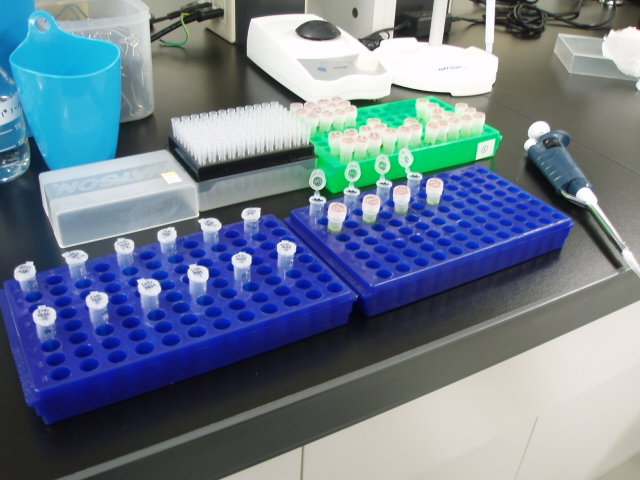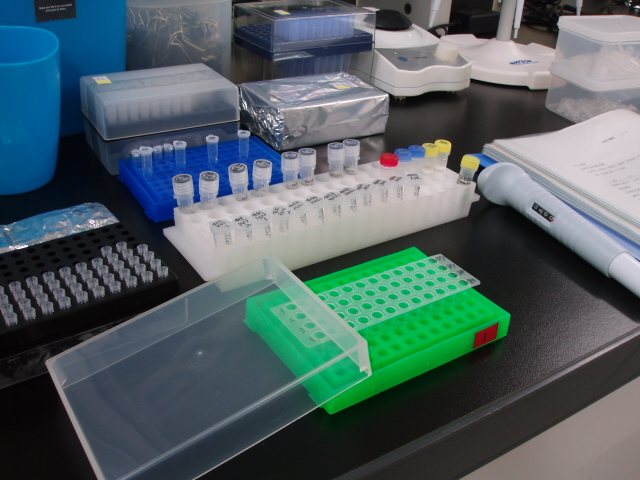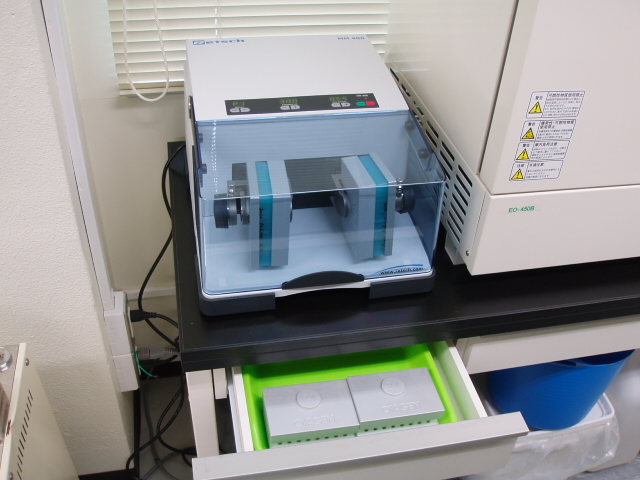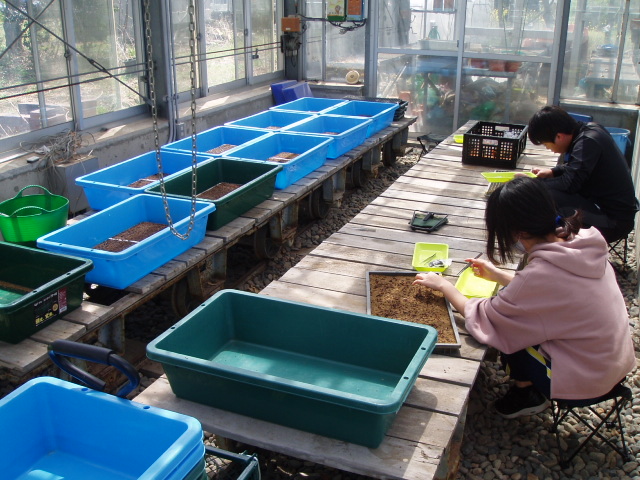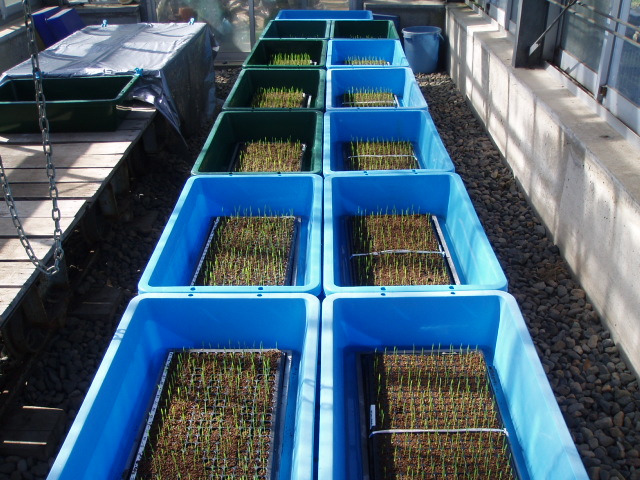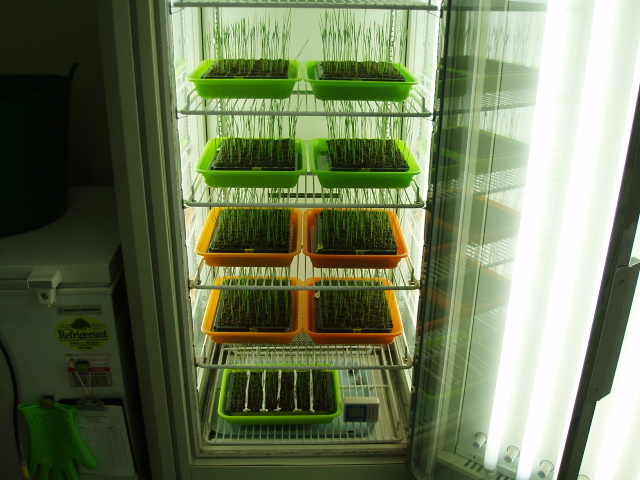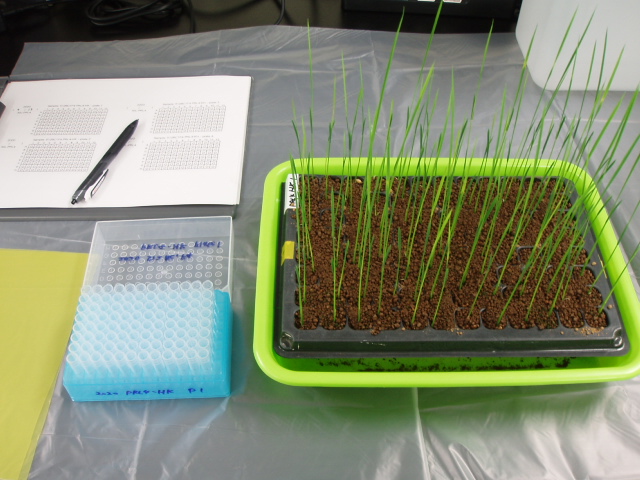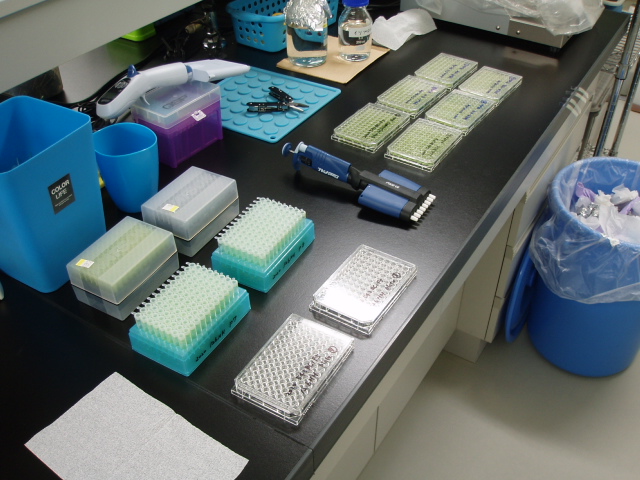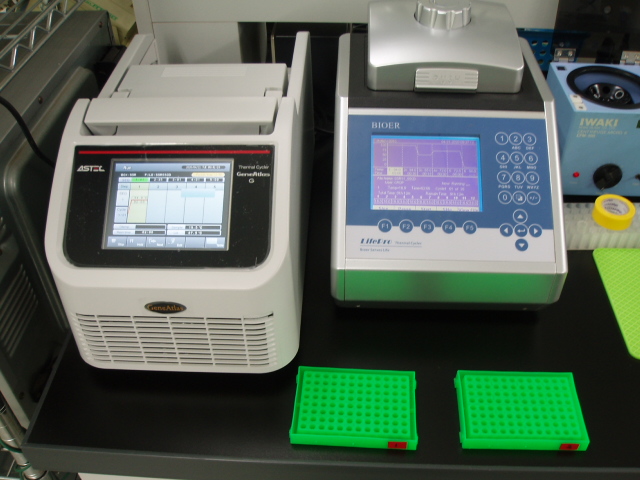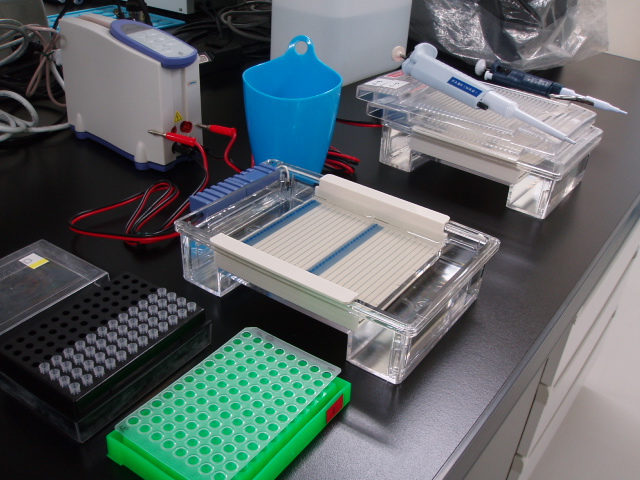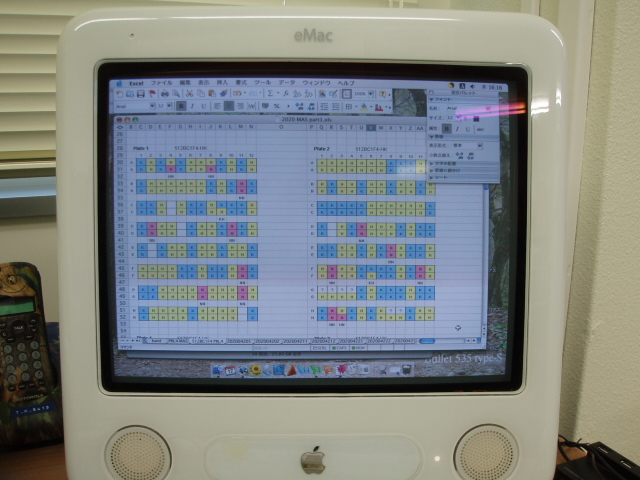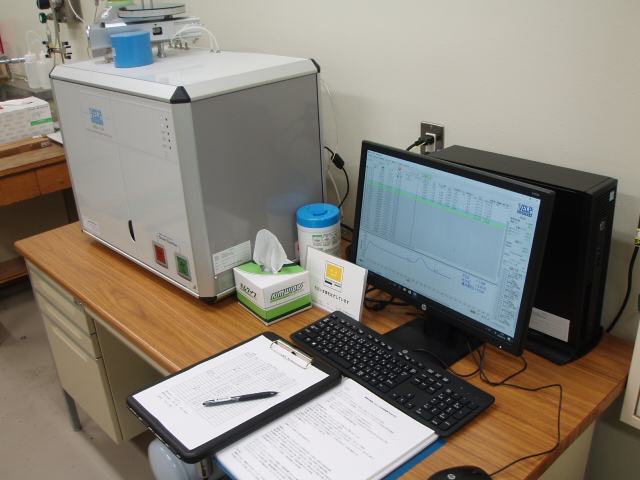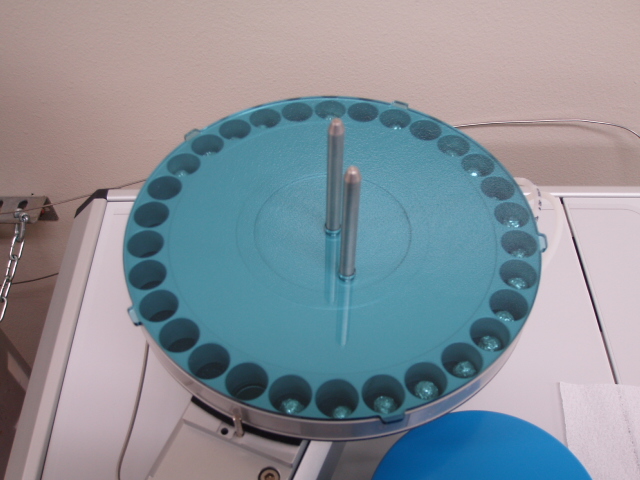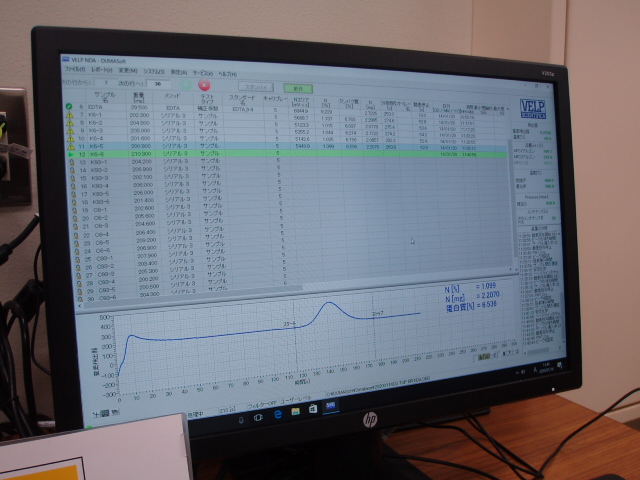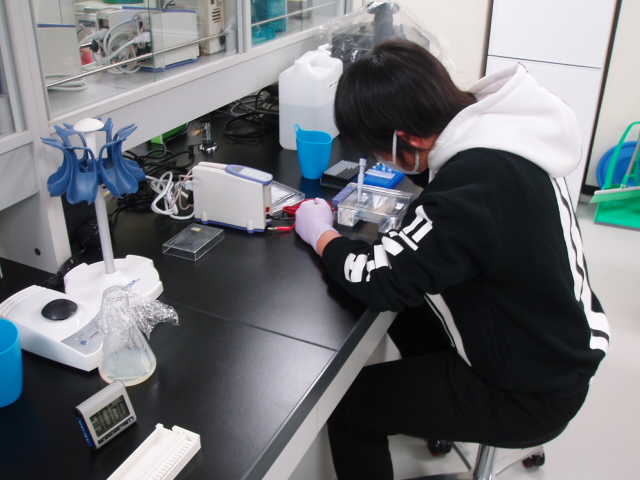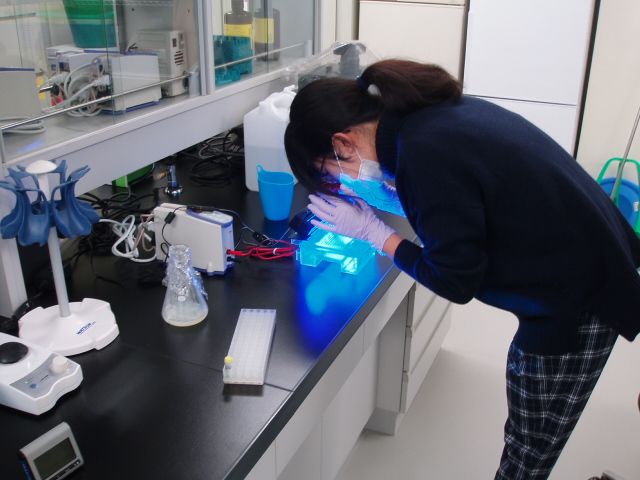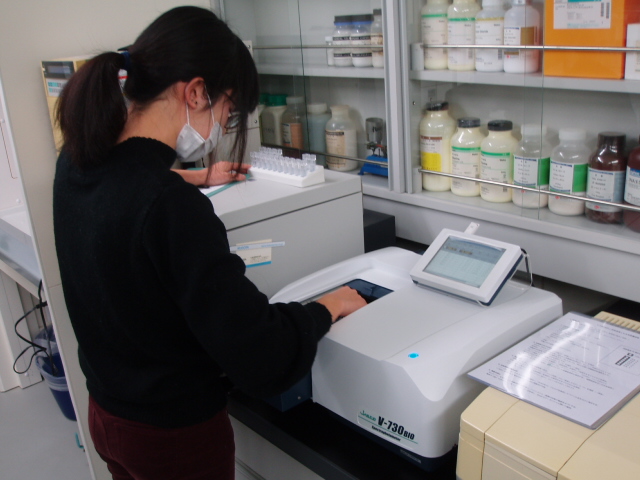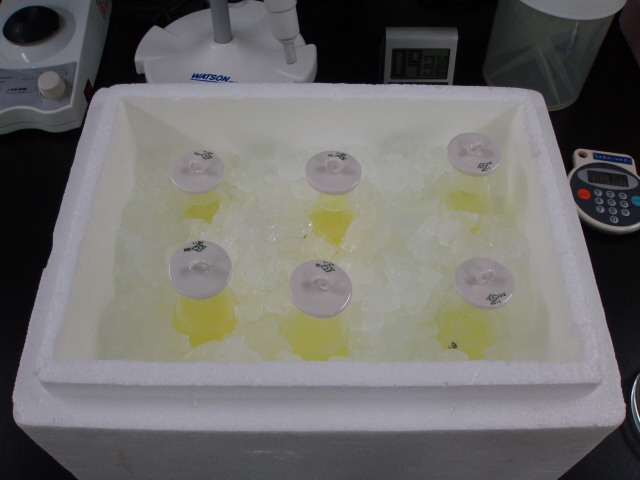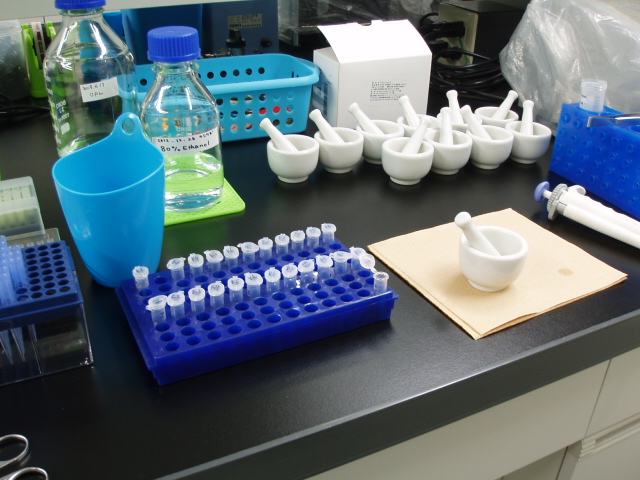今年の7月は雨、雨、雨。
蒸し暑く、不快指数が高い日が続いております。
雨の降らない日を利用して圃場作業を実行。
7月にやるべきことは、除草、支柱立て、防鳥糸張り。
除草作業は土壌表面を削いで除草するピーラーのような器具を使用。
全長が約1.9mあるので広い範囲に対応できて非常に便利です。
週1回の除草作業を落水するまで続けていきます。
つづいて支柱立て。
今年立てた支柱は354本。
2日に分けて行いましたが、今年は炎天下の作業ではないので少し楽でした。
最後に防鳥糸張り。
例年通り黄色の防鳥糸を使用し、支柱に設置。
8月から出穂するので圃場作業だけでなく、実験も始まります。
日照不足が気になるので、早く梅雨が明けて欲しいですね。